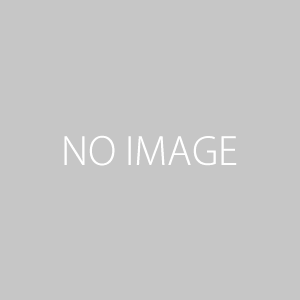視座・視点

2019.2月 教室だよりより
☘
物事は見る視座や視点によって捉え方が変わります。
考え方が短絡的で一方通行になると
視野が狭まり、
時として自分を苦しめることや成長を阻害することになります。
教室では学年問わず仲が良く、
互いに切磋琢磨する姿も時に支え合う姿も見られます。
400人規模の小さな学校ですし、
その関係性はもとより深く濃密です。
教室ではそれがさらに凝縮され、
狭い教室の中でより距離が縮まります。
☘
開業当時から変わらぬ想いでいますが
家族のように思う子どもたちは教室の中では言うなれば兄弟のようなもので、
上の子が下の子の面倒をみるという家族間での構図や小さな社会での自然なあり方は、心地よく心強いものであると思います。
一方でそこに依存してしまうと、自分の意思というものがなくなることもあります。
馴れ合いの中で共に雪崩のように崩れていくことも、他者を理由に我を見失うことも、本当にごく稀ですがないわけではありません。
調和の中に在りながら、個で闘う。
そこにきちんと自分の意思と目標をもって学習に取り組む必要があります。
☘
振り返り自分が通う小学校と近隣2校の生徒が通うマンモス教室にいた私としては、いまの教室の子どもたちがとても羨ましく思います。
大勢の中にポツンと一人はやっぱり寂しいものがあります。
どこに焦点をおくかによって、
変わるものがあるとここでもわかります。
☘
究極の面倒くさがりで時短人間の私は、
消しゴムを使うのが嫌いです。
収集癖がある私は子どもの頃、消しゴムはたくさん持っていましたが、とにかく消しゴムを使わないのでコレクションのように綺麗に飾られていました。
消しゴムを使いたくない理由は、
面倒だし時間がかかるから。
消しゴムを使わないために
学校では間違わずに板書を書き写し、
公文のプリントでもかなり意識して問題を解いていたと思います。
☘
消しゴムを使わない習慣のメリットは、
授業では聴くに専念できること。
板書の書き写しに時間がかからないため
効率よく学習できました。
思考も乱雑にならずに済みます。
リズムやテンポが崩れないのも良さかと思います。
☘
【消しカスは努力の証、消しカスはケアレスミスの証】
進学塾では消しゴムを使わない指導をすることが多いです。
間違えたところは消しゴムで消さずにバツをつけたり二十線を引いたりして、改めて別に書き直します。
どこでつまずき、どこで間違えたのかを認識させるのです。
もう一つの理由は言わずもがな、時間の短縮。
圧倒的な勉強量の中で
消しゴムで消す時間・鉛筆を持ち直す時間・思考を再整理する時間は塵も積もれば山となり、
かなり無駄な時間を浪費するということは早期から意識させ改善させていくのが望ましいと思います。
消しカスの量を見て
頑張ったね♬と声をかけるのか、
消しゴムを使わないで済むように導くのか…
どちらも必要で偏ってはいけない。
その時そのタイミングによっていろんな視座から見たピンポイントな視点で必要な言葉をかけていきたいです。
とはいえ、消しカスが床に散らばっているのを見ると「お作法がなっていません!」と叫びたくなる私☆
いや、叫んでいます(笑)
mana