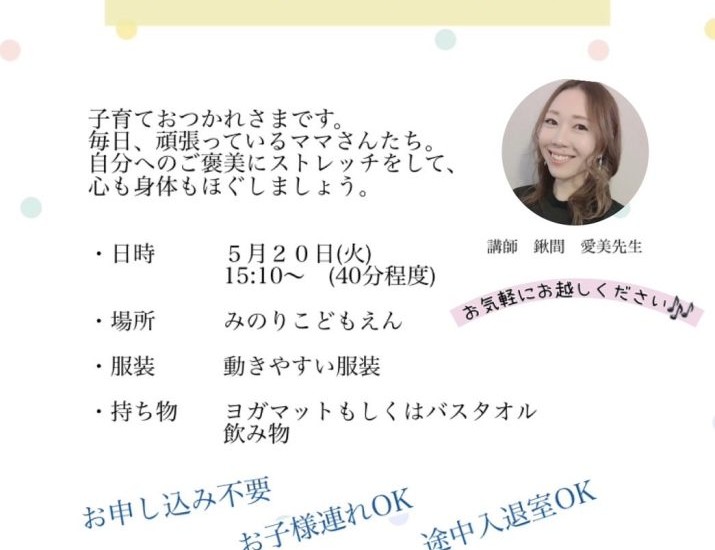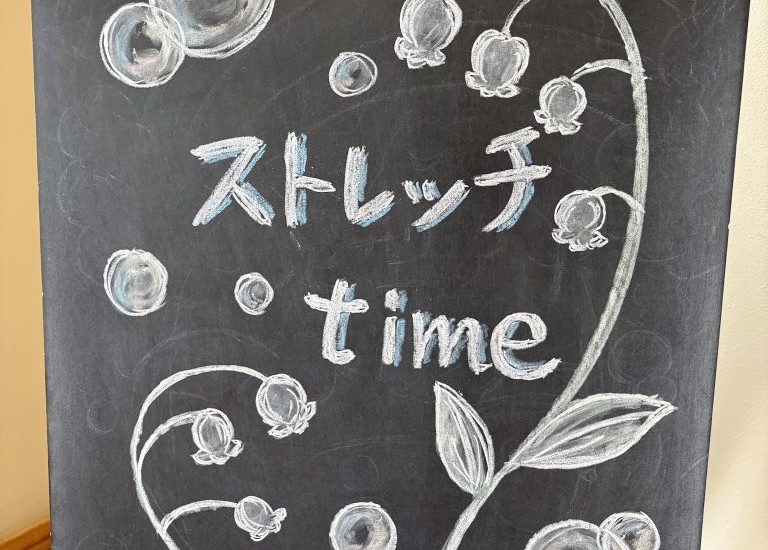土踏まず

【土踏まず】
左右対称であるかを
気にしたことはありますか?
左右対称であるかのチェック方法には、
①左右の足の甲の高さを見比べる
②立った時の足裏の接地面積の感覚
③体育座りで足裏を床につけて、ボールペンなどを土踏まずに差しこみ、入り具合を見る
などがあります。
・
・
・
土踏まずの役割には、
✅体重を支える
✅姿勢のバランスをとる
✅地面からの衝撃を吸収する
✅歩行を含む動作時のバネとなる
などがあります。
土踏まずの状態によっては
❌靴擦れ
❌足の痛み
❌足指や爪の変形
❌ウオノメやタコ
❌外反母趾
といった足トラブルを招いたり、
❌膝・股関節・腰の痛み
など全身に痛みの連鎖が起こります。

土踏まずが適度にある理想的な足をもつ日本人は約1割しかいないと言われています。
図のように、かかとの骨である『踵骨(しょうこつ)』の傾きは土踏まずの状態によって変わります。
踵骨の角度が足の甲と足首の捻れに影響し、
それらと連動して膝も捻れます。
股関節が柔軟であれば股関節よりも下の各関節の捻れをある程度吸収できますが、股関節が硬いと膝に捻れの大きな負担がかかり膝痛を引き起こします。

膝が不安定になると、
肩こりや腰痛が起こり、
さまざまな関節へ痛みの症状が広がります。
図の膝の位置と足首に注目してみてください。
土踏まずの状態は、
かかとの変形につながり、
動きそのものや
動作のバランスを変えてしまいます。

扁平足の人を後ろから見ると、
足全体が内側に大きく歪んでいます。
図でいうと、一番左側の状態です。
外反母趾が進行しやすいです。
靴底のかかとは内側から減りやすく、
歩くとすぐに疲れたり、
就寝時や寝起きに
こむら返りが起きやすくなります。
🦶
甲高の人は、足全体が外側に歪みます。
図でいうと、一番右側の状態です。
靴底は外側から減りやすく、
捻挫をしやすい…または捻挫経験のある人に多いかかとの形になります。
甲高足タイプに合う靴は日本に少なく、
靴紐で内出血を起こしたり、
サイズ選びが難しいため足トラブルが起きやすいです。
・
・
・
自分のかかとが歪んでいるかをチェックするには、鏡に背を向けて立ち、足を腰幅に開き、前屈をします。
いわゆるアキレス腱が床に対して垂直に見え、
その延長線上に膝裏の真ん中があり、
さらにその延長線上に坐骨があれば
良い状態❣️
歪んでいたら、
まず自分は扁平足と甲高のどちらのタイプなのかを確認しましょう。
いずれにしても、
足の裏・脛・ふくらはぎの筋肉をやわらかくし、
そしてトレーニングすることが大切です。
足の裏をほぐす際は、
土踏まずだけでなく
①指のつけ根
②親指側の側面
③小指側の側面
④かかと周辺
も、しっかりとほぐしましょう!
・
・
・
土踏まずが左右対称でない場合、
顔のパーツバランスも非対称になりやすいです。
足を整えれば顔も整います♪