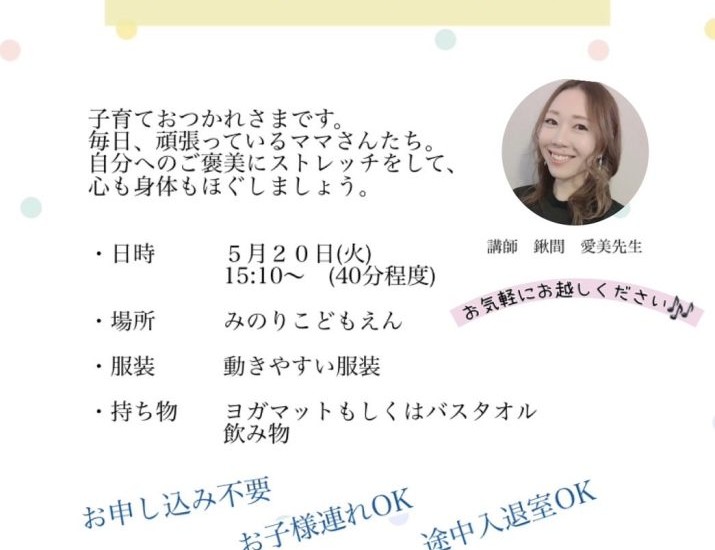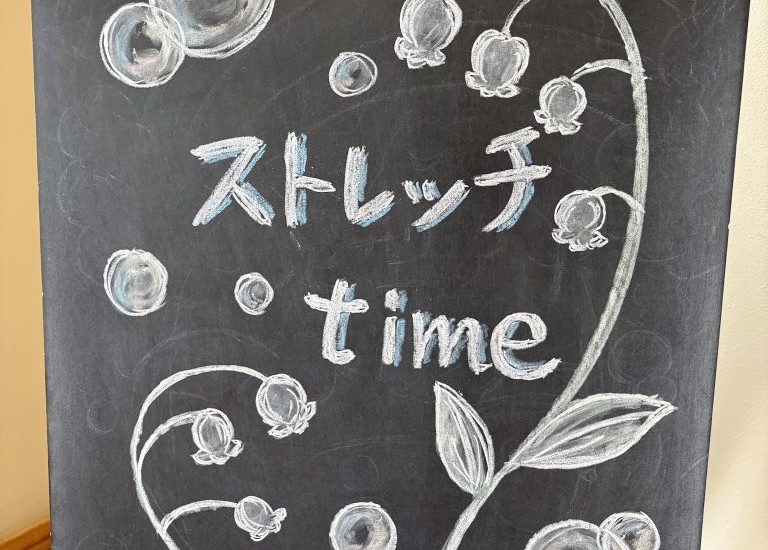しゃがむ

整形外科疾患の検査項目には以前からずっと脊柱側弯症や胸郭の項目がありましたが、平成28年の春に四肢・骨・関節の運動器についての検査も加わりました。
小学校などでも春の検診時期になると
これらの項目について問診があります。
しゃがみこみテストは、
下腿の筋肉の柔軟性がチェックできます。
しゃがむ際には、股関節・膝関節・足関節が曲がることが必要になります。
特に足関節の可動域の柔軟性は、
しゃがめるかどうかに大きく影響します。
しゃがめても踵が浮いてしまうのは、
しゃがめたことになりません。
しゃがめない=下半身の関節の可動域が狭い
これは歩行の質にもつながります。
・
・
・
中学生くらいになると成長期のピークを迎えることから、骨の成長スピードが早まります。
この成長スピードに筋肉・腱・靭帯など骨とつながる組織の成長が追いつかないと、各組織は過緊張を起こし柔軟性を失います。
この状態のまま、激しい運動をすることで大きな怪我を招くこともあります。
・
・
・
しゃがめない原因には、
生活様式の変化もあります。
日本人特有の和の文化は、日常生活の中でも足関節や股関節の柔軟性を高めるものでした。
低い姿勢で動作をする習慣が少なくなり、重力を正しく受けた自然な動作が難しくなってしまいました。
今後はさらに、便利な道具に頼りすぎることで関節や筋肉を動かす時間が減っていくことが懸念されます。
動かす必要性がなくなれば、
その部位は機能しなくなります。
『動く部位は丁寧に動かし続けるということが一番体にとって優しい』ということを忘れずにいたいです。
・
・
・
しゃがめない状態は
そのままにしておいてはいけません。
しゃがめないということは、股関節・膝関節・足関節をうまく使えていないということ。
そのまま運動を続けたり、体を動かし続けることは、筋肉・腱・靭帯・骨に大きな負担をかけます。
学生でスポーツをしている子がいたら、
しゃがめるかをチェックしてください。
しゃがめない場合は、
まずは特に足指と足首をほぐすためによく動かし、そして回します。
スムーズにしゃがむためには
●骨盤が立つ感覚を養う
●背骨を立て伸ばし胸を引き上げられるようにする
●股関節・膝・足の人差し指の方向を揃える
これらも大切です。
足を揃えて、
目線を正面に向けたまま、
踵が床から離れないようにしながら
すっとしゃがみ、すっと立てるのか。
一生歩けるのかどうかにも関わってくるので、
結果を恐れずトライしてみてください。